 生物工学一般
生物工学一般 胸腺の機能がその形態を形成することを示すモデル(Biophysics: function of thymus gives rise to form)
2025-06-23 ミュンヘン大学(LMU)ルートヴィヒ・マクシミリアン大学(LMU)の研究者は、胸腺の巻き状構造が、自己組織化によって形成されることを理論モデルで示した。この構造は自己反応性T細胞を効率的に除去する機能と密接に関係し、機...
 生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般 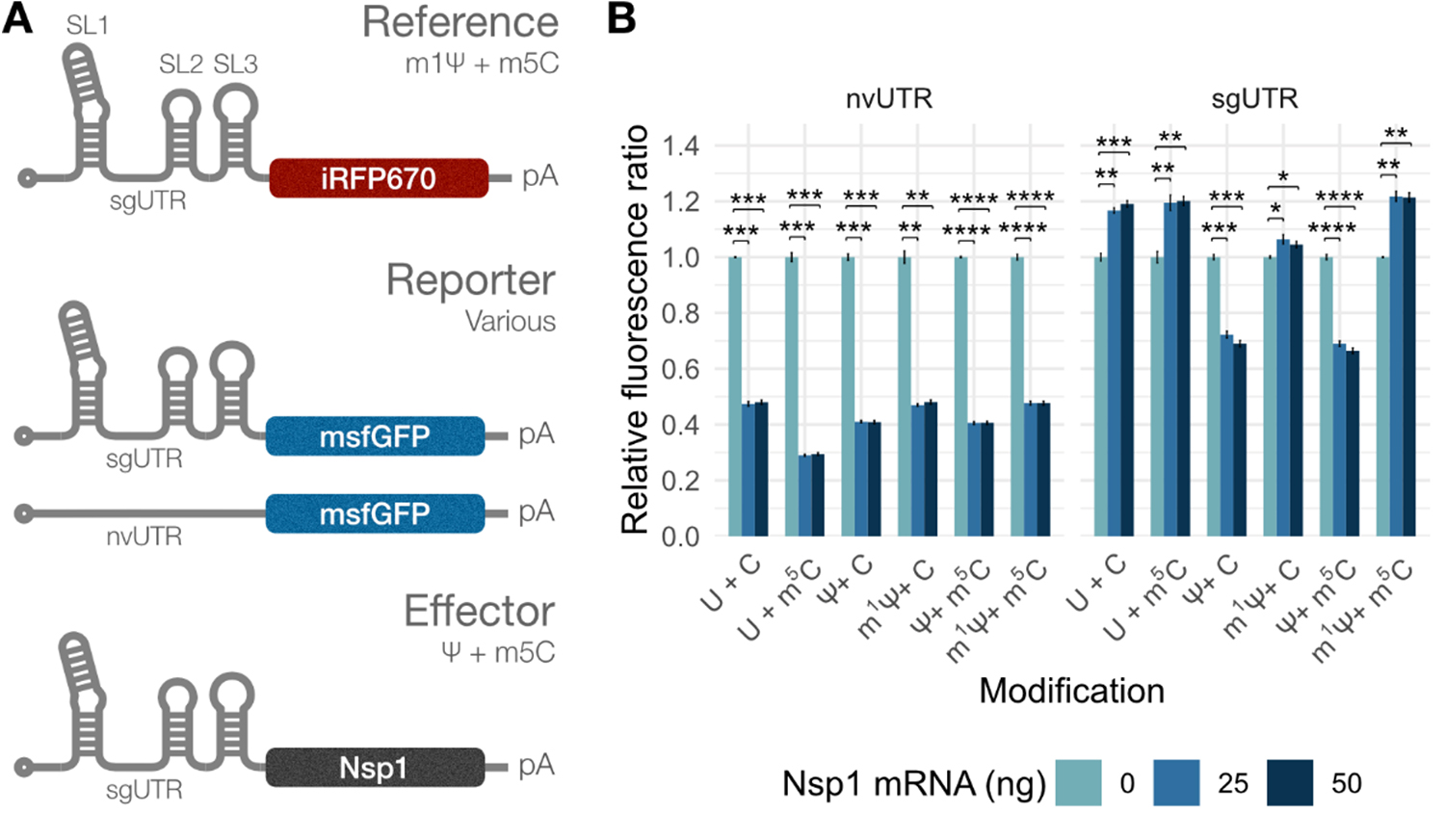 生物工学一般
生物工学一般 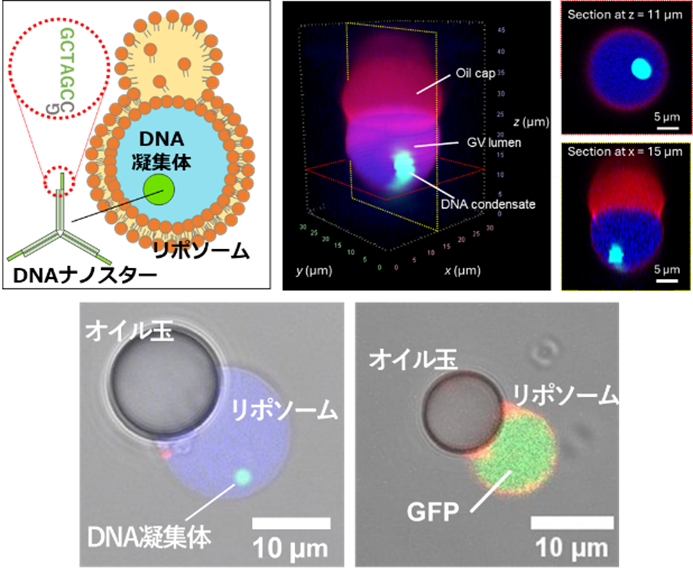 生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般 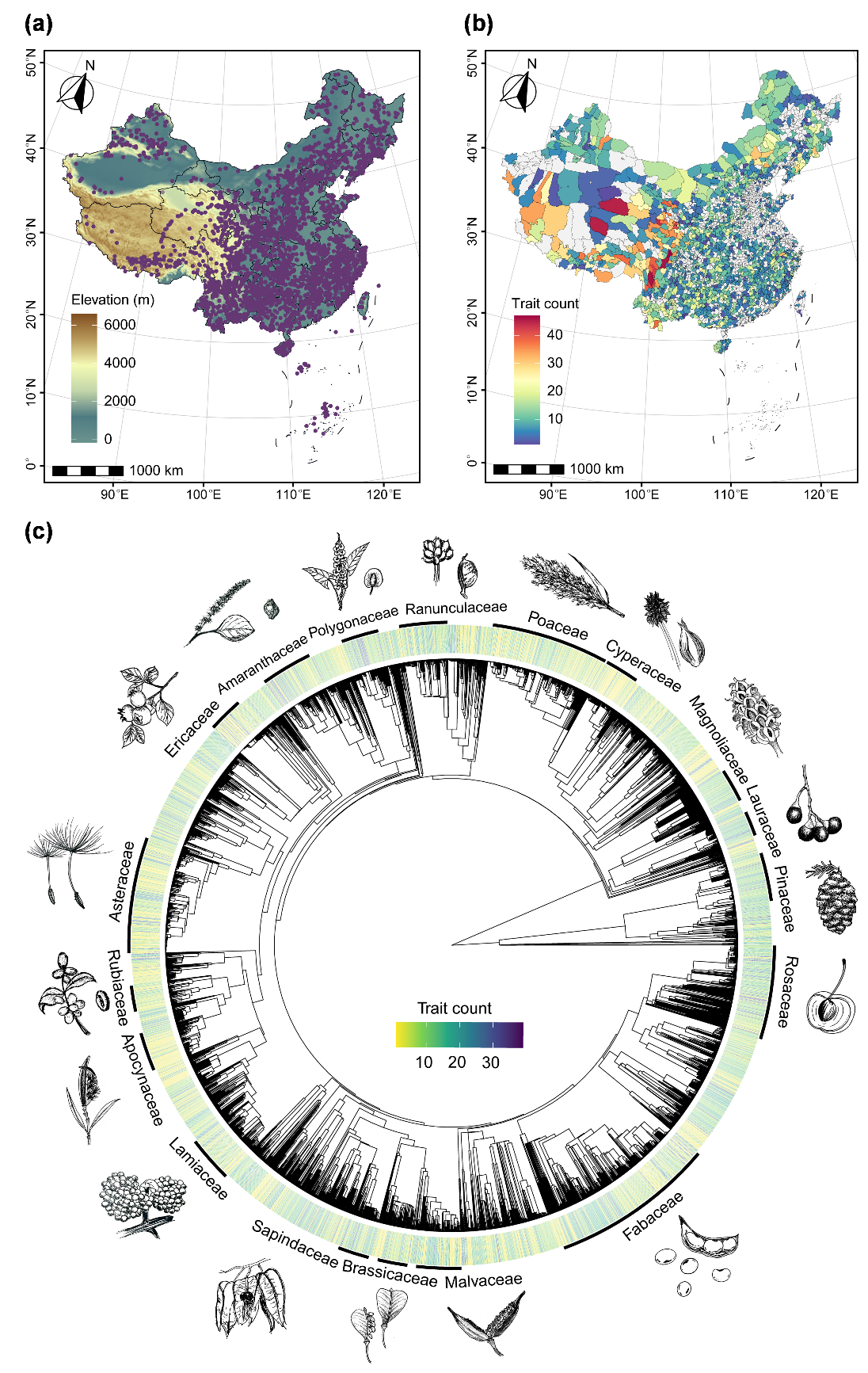 生物工学一般
生物工学一般 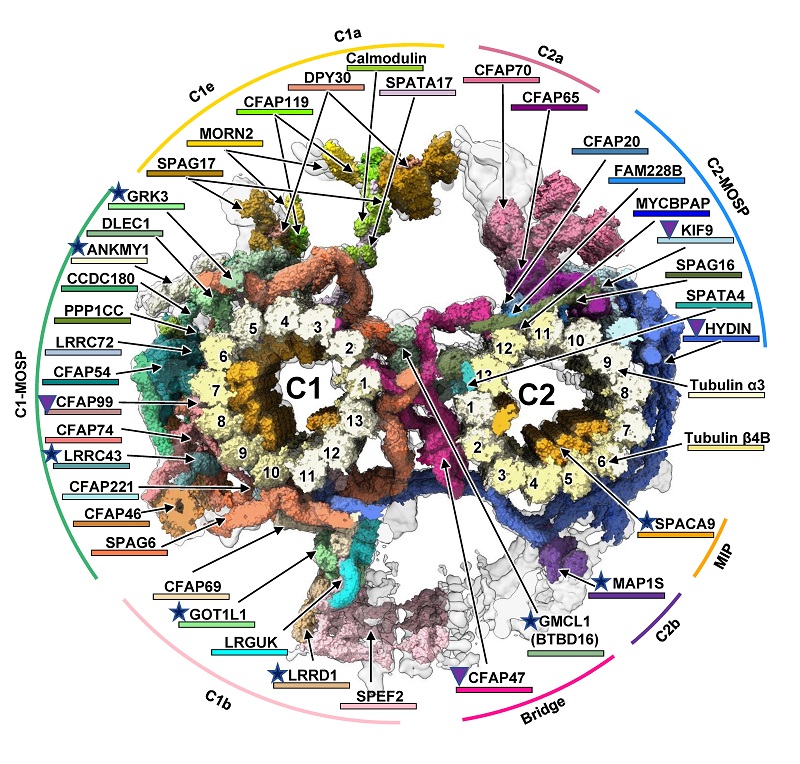 生物工学一般
生物工学一般 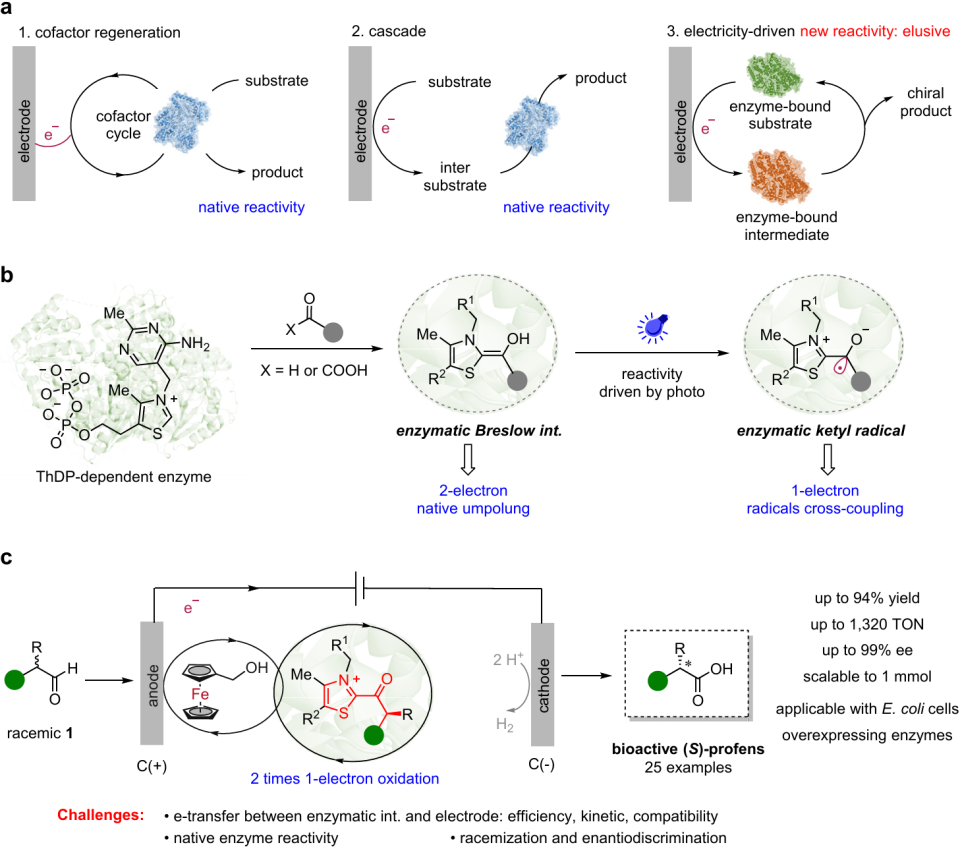 生物工学一般
生物工学一般 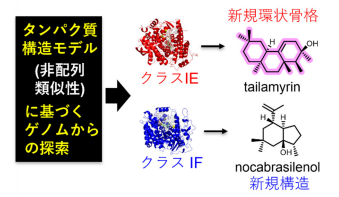 生物工学一般
生物工学一般