 生物工学一般
生物工学一般 博物館標本から世界的な蝶の病気の拡散を特定(Museum collections reveal worldwide spread of butterfly disease)
2025-04-02 ジョージア大学ジョージア大学(UGA)の研究者たちは、博物館に収蔵された約3,000点の蝶の標本を分析し、寄生虫Ophryocystis elektroscirrha(OE)の世界的な分布を追跡しました。この寄生虫...
 生物工学一般
生物工学一般 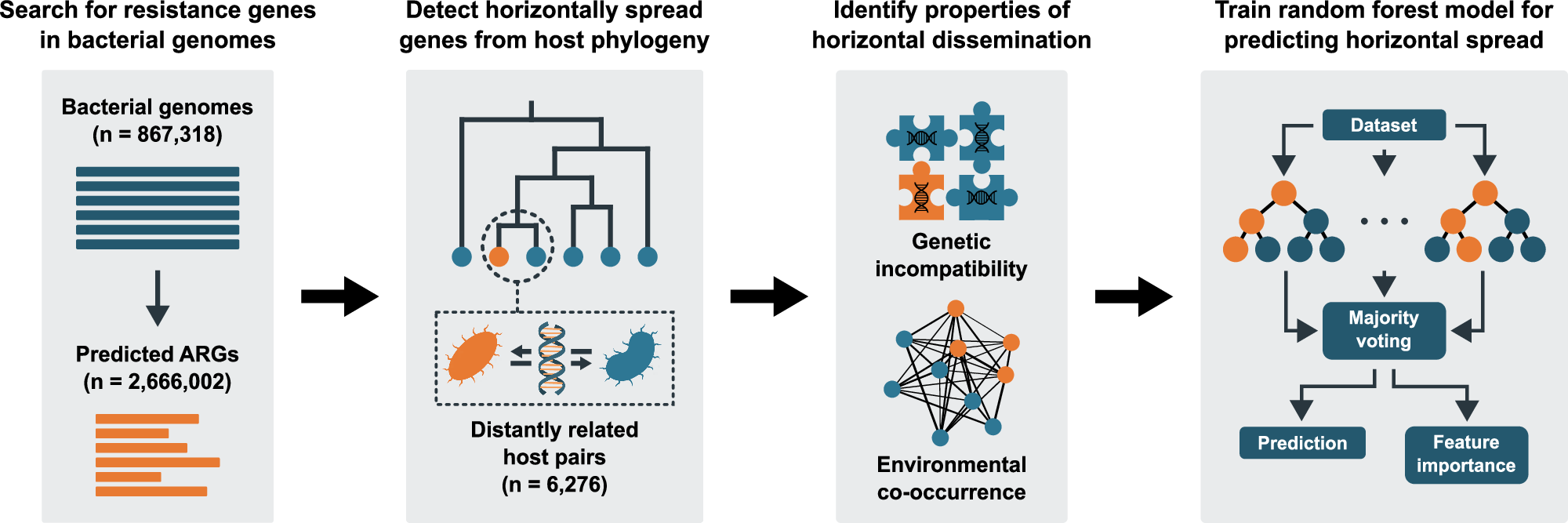 生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般 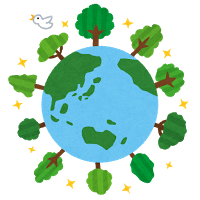 生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般 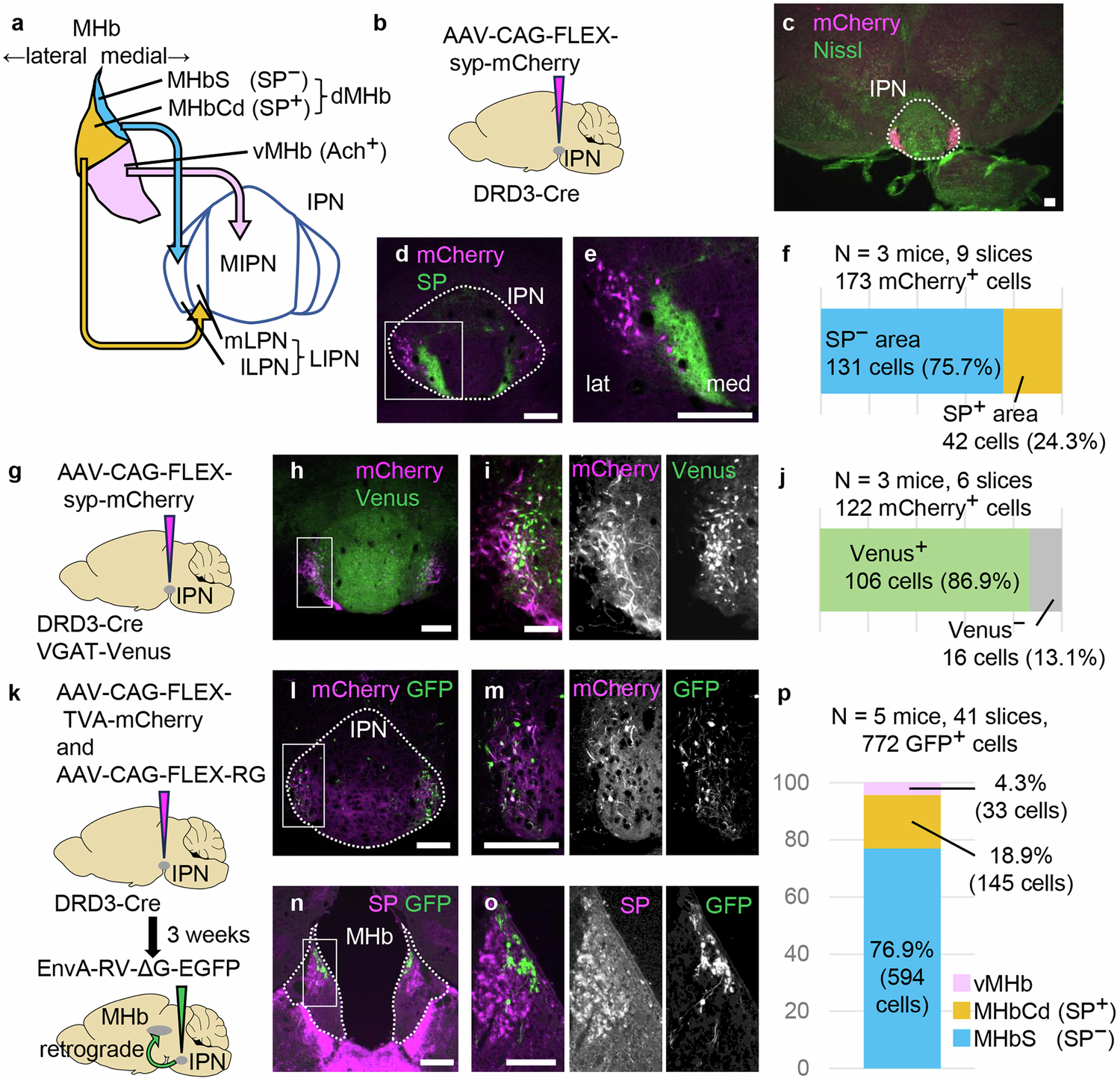 生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般  生物工学一般
生物工学一般