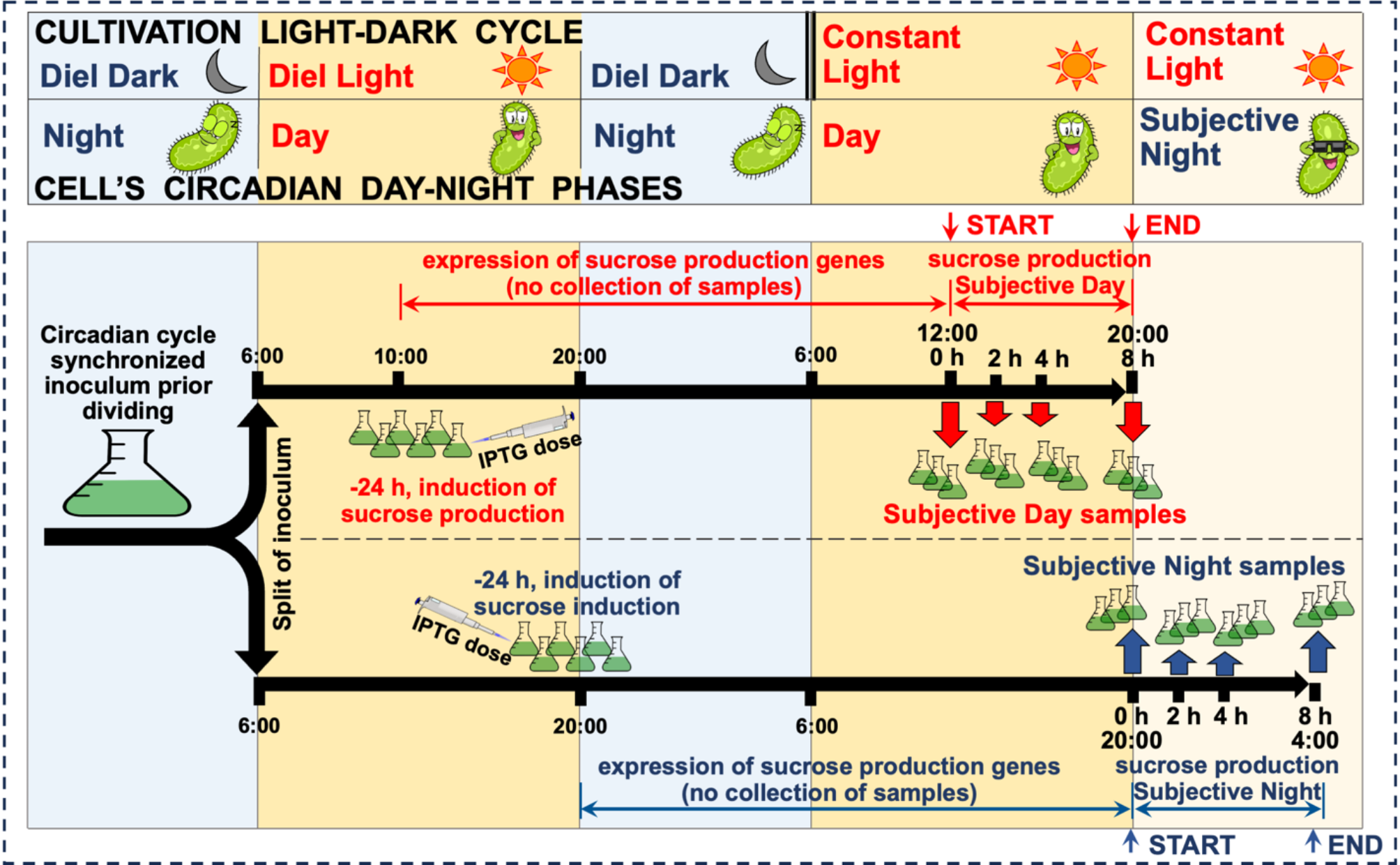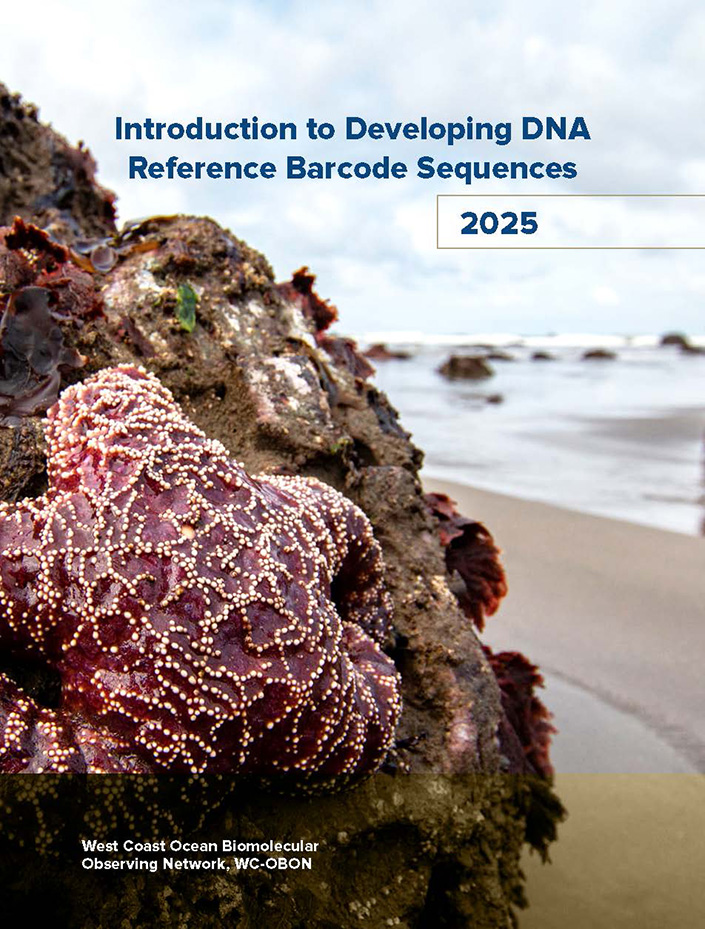生物工学一般
生物工学一般 哺乳類視床下部発達における進化保存性と革新性を解明(Researchers Unveil Evolutionary Conservation and Innovation in Mammalian Hypothalamus Development)
2025-04-09 中国科学院(CAS)中国科学院遺伝・発生生物学研究所の呉慶峰教授らは、哺乳類の視床下部発達における進化的保存性と革新性を明らかにしました。研究では、ヒトとマウスの視床下部における神経前駆細胞の発生過程とその遺伝的特徴を...