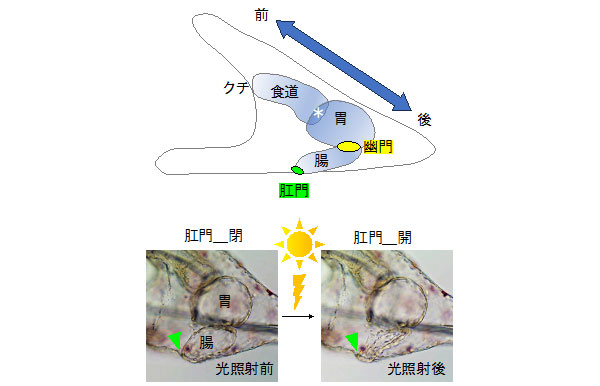2024-10-21 東京大学
【ポイント】
○ 細胞内でタンパク質を集積化し相分離液滴を形成するペプチドタグを開発
○ アクチン重合を促進する液滴の機能と流動性の関係を解明
○ 細胞内の相分離液滴形成・制御機構を解明する分子ツールとして有用
【概要】
東京工業大学* 生命理工学院 生命理工学系の三木卓幸助教(現 東京大学 大学院工学系研究科 特任講師)、橋本匡浩大学院生(研究当時)、東京科学大学 三原久和名誉教授の研究グループは、細胞内で相分離液滴(用語1)を作るペプチドタグ技術を開発しました。
細胞内では、タンパク質やRNAといった生体分子が集合し、数百nm〜数µmスケールの液滴と呼ばれる構造体を形成します。近年の研究により、多様なタンパク質が液滴を形成しうることが判明してきましたが、その形成メカニズムや生理的意義は依然として多くの謎が残されています。本研究では、このミステリアスな液滴を細胞内で簡便に人工構築するペプチドタグ手法を開発しました。
今回、研究グループは、可逆的に集合・解離する自己集合性ペプチド(用語2)としてYKペプチドを開発しました。YKペプチドは、チロシン(Y)とリシン(K)を交互に繰り返した配列からなる7〜15残基の人工ペプチドです。YKペプチドを緑色蛍光タンパク質(sfGFP)にタグとして融合すると、YK-sfGFPは細胞内で液滴を形成しました。またYKの鎖長を変えることで液滴の流動性を制御でき、さらには複数のタンパク質にYKペプチドタグをつけることで多成分からなる液滴を細胞内で構築することに成功しました。研究グループはこの技術を用いて、アクチン重合反応を担うNck1/N-WASP液滴を細胞内で人工構築し、その流動性と機能との関連を明らかにしました。本研究によって開発されたペプチドタグ技術は、合成生物学(用語3)研究における相分離液滴形成ツールとして広く利用されることが期待されます。
今回の成果は、英国科学誌「Nature Communications」のオンライン版で10月18日(現地時間10時)に公開されました。
*2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。
背景
生命の最小単位とされる細胞には、脂質膜に覆われずにタンパク質やRNAなどが集積した「非膜オルガネラ」と呼ばれる集合体が存在します。非膜オルガネラは液-液相分離現象によって生じ、球形で流動的な特徴を持つことから相分離液滴とも呼ばれています。相分離液滴は、細胞の一過的なストレス応答に関与し、神経疾患の原因物質とされるアミロイド(用語4)の形成にも関連することが知られ、その生理的意義の解明や制御は重要な課題です。近年では、人工的にタンパク質群を集積化させ、相分離液滴を細胞内で再構築する合成生物学研究が重要視されています。しかし、相分離液滴を分子レベルのデザインで再構築した事例は極めて限定的であり、また、アミロイド形成に関わるβ-シートペプチドを用いて液滴構築に成功した報告はありませんでした。
研究成果
液-液相分離する天然のタンパク質の幾つかは、自己集合してアミロイド様の構造体を形成します。さらに、この構造は容易に崩壊する「可逆的なアミロイド」であることが知られています。三木博士・橋本博士・三原名誉教授らは、可逆的なアミロイドを形成するペプチドを開発すれば、細胞内で人工的に相分離液滴を構築する分子ツールになると考えました。具体的には、疎水性のチロシン(Y)と正電荷を帯びるリシン(K)を交互に繰り返したYKペプチドを設計しました(図1a)。一般的に、疎水性アミノ酸と親水性アミノ酸を繰り返すと、両親媒性のβ-シート構造(用語5)を形成することが知られるため、YKペプチドはアミロイド構造に見られるβ-シート構造を形成しやすいと想定できます。また、正電荷を帯びるリシンを繰り返すことでペプチドタグ間に静電反発を導入し、不可逆的なアミロイド形成を抑制しました。
本研究ではさらに、13残基から構成されるYK13ペプチドがタンパク質を集積化し、液滴を形成するタグとして機能するかを検討しました(図1a)。集積させるモデルタンパク質として緑色蛍光タンパク質(superfolder GFP、sfGFP)を用い、N末端に核排出シグナル(NES)、およびYK13ペプチドを導入したNES-YK13-sfGFPを設計しました。この遺伝子をコードしたプラスミドDNAを哺乳類細胞COS-7細胞に導入したところ、細胞内から球状の集合体が観察されました(図1b)。この集合体が流動性のある液滴であることを、光褪色後蛍光回復法(FRAP)(用語6)から明らかにしました(図1c)。以上から、YK13ペプチドをタンパク質に融合することで、人工的な相分離液滴を形成できることが判明しました。

図1 細胞内でのYK13ペプチド融合sfGFPの液滴形成。(a) NES-YK13-sfGFPの構造とYK13ペプチドの化学構造。(b) NES-YK13-sfGFPを発現した細胞の共焦点蛍光顕微鏡観察画像。細胞の中で多数の液滴が観察された。Scale bar = 20 µm (c) FRAP実験による流動性評価。集合体の一部(赤枠)にレーザーを照射し(00:01)、その褪色した領域での蛍光強度が分子拡散によって徐々に回復する様子が捉えられた。Scale bar = 2 µm
次に、細胞内でYK13ペプチドがどのような相互作用で集合するかを検証するべく、単離・精製したYK13-sfGFPを使って試験管内で液滴形成を評価しました。YK13ペプチドは正電荷を帯びてペプチド間に静電反発が生じるため、YK13-sfGFPの集合は認められませんでした。一方、アニオン性の負電荷を帯びるATP(アデノシン三リン酸)の添加に伴って自己集合し、20 nm程度のオリゴマーを形成しました(図2a、b)。また、細胞は生体分子が30-40%の体積を占有する混み合った環境であるため、これを模倣するためCrowding剤であるポリエチレングリコール(PEG20k)を添加したところ、YK13-sfGFPは液滴を形成しました(図2c)。これらの結果から、YK13-sfGFPは細胞内のATPとの静電相互作用によってオリゴマーとなり、Crowding環境でオリゴマーが集まって数µmサイズの液滴に成長することが判明しました。また、この液滴はATP依存的であるため、ATP分解酵素を添加すると、液滴が消滅することを明らかとしました(図2d)。

図2 精製YK13-sfGFPを用いたテストチューブ内での液滴形成。(a) ATP添加に応じたYK13-sfGFPの自己集合。(b) 動的光散乱法によるYK13-sfGFPの流体力学半径測定。6 nmサイズのタンパク質がATP添加に伴って集合し、半径が20 nmに増大した。 (c) ATPとCrowding剤(PEG20k)の添加に伴ったYK13-sfGFPの液滴形成。(d) ATP分解酵素存在下での可逆的な液滴形成と崩壊。ATP分解酵素を含む条件(赤)では、ATP添加時(▼矢印)に一過的に液滴形成による濁度上昇が見られ、その後のATP分解によって液滴が崩壊し濁度が減少する。一方で、分解酵素を含まない場合(灰)では、濁度の減少は見られない。
さらに、筆者らはYK13ペプチドを用いることで、多成分からなる液滴を容易に作成できることを示しました。具体的には、蛍光波長の異なる3つの蛍光タンパク質としてsfGFP、mCherry、miRFPにYK13ペプチドを融合して共発現すると、3色が重なり合った液滴が細胞内で形成されました(図3)。

図3 YKペプチド融合による多成分からなる相分離液滴作成。直線上で3色の蛍光パターンが同一であり、共局在していることが分かる。
最後に、YK13ペプチドを使って、天然の細胞内で見られるNck1タンパク質(用語7)とN-WASPタンパク質(用語8)から構成される液滴を、細胞内で人工構築しました(図4a)。このNck1/N-WASPによる液滴は、細胞骨格であるアクチンの重合を促進することが知られていますが、液滴の柔軟性・流動性がどのようにアクチン重合反応に影響するかが十分に検討されていませんでした。そこで、筆者らは、鎖長の異なるYKペプチドを用いて、Nck1およびN-WASPを集積させた液滴を細胞内で形成させ、流動性とアクチン繊維量の関係を細胞内で評価しました。その結果、N-WASPの運動性が低下する条件で、顕著にアクチン繊維量が増加しました(図4b)。以上から、YKペプチドタグを用いることで、設計通りの液滴を細胞内で容易に作成でき、液滴の機能評価を実現できることが示されました。

図4 YKペプチドタグを用いたNck1/N-WASP液滴の再構築実験。(a) YKペプチドタグによるNck1/N-WASP液滴の細胞内構築。(b) YKペプチドタグ融合によるアクチン繊維量の増加。Nck1とN-WASPともにYK9ペプチドタグを融合した条件で、アクチン繊維量が顕著に増加した。
社会的インパクト
今回報告したYKペプチドは、わずか7〜15残基の小さいペプチドです。相分離液滴を形成する天然のタンパク質は一般的にこの10倍以上も長く、本研究で得られた結果は、タンパク質主鎖の絡まり合いが重要とされていた相分離現象における常識を打ち破る驚くべき内容です。YKペプチドは著しく小さいため、容易に遺伝子導入でき、また鎖長を変えることで相互作用を適切に調節できます。YKペプチドタグは、今後の相分離液滴の研究において基盤的な分子ツールとして強力だと考えられます。特に、近年の報告ではヒトプロテオーム(用語9)の3割のタンパク質が液滴を形成しうると試算されており、その大半が実験的に証明されていません。YKペプチドを用いることで、これらのタンパク質が細胞内でつくる液滴の構造や形成機構を明らかにできると期待できます。相分離液滴は、神経疾患の原因物質となるアミロイド形成にも関わることから、本技術の応用によって、これらの形成メカニズムにも貢献できうると想定されます。
今後の展開
上記で述べたとおり、液滴形成が実験的に証明されていないタンパク質は多く存在します。筆者らは、これらのタンパク質にYKペプチドタグを融合し、細胞内でどのような液滴を作り得るのかを検討する予定です。これによって相分離液滴の全貌を徐々に解き明かし、細胞内で不均一な相を作る意義や役割の本質を調べます。これが将来的に、神経疾患などの治療や細胞工学に貢献できると期待できます。
付記
本研究成果は、東京工業大学OFC(オープンファシリティーセンター)の協力によって得られたものです。また、本研究は、JSPS科学研究費助成事業(若手研究(21K14739)・特別推進研究(23H05408)・特別研究員(23KJ0920))、JST創発的研究支援事業(JPMJFR2251)による研究助成の多大なる支援や、花王株式会社からの支援を受けて実施されました。
【用語説明】
(1)相分離液滴:タンパク質や核酸などが相互作用して形成される膜を持たない構造体。液-液相分離によって形成され、流動性を持つ液滴としての物性を持つ。
(2)自己集合性ペプチド:水素結合や疎水性相互作用などの非共有結合によって、自発的に規則性を持つ集合体を形成するペプチド。
(3)合成生物学:天然に存在する分子、分子集合体、システムを模倣し作製することで生命原理を明らかにする学問。
(4)アミロイド:タンパク質の変性などで生じる不溶性の凝集体。繊維状の構造体であり、体内に蓄積することでアルツハイマー病や狂牛病の原因物質となりうる。
(5)β-シート構造:タンパク質二次構造のひとつである。複数の伸びたペプチド鎖が並行もしくは逆並行に相互作用して形成されるジグザグ状の直鎖構造。
(6)光褪色後蛍光回復法(FRAP):強い励起光によって蛍光分子を褪色させ、その部分の蛍光回復を観察することで分子拡散を見る。
(7)Nck1タンパク質:リン酸化チロシン認識ドメインであるSH2(Src-homology 2)ドメインと、プロリンリッチモチーフと結合する3つのSH3(Src-homology 3)ドメインから構成されるタンパク質であり、細胞遊走などにおいてアクチンフィブリル細胞骨格の形成に関与する。
(8)N-WASPタンパク質:Nck1タンパク質との相互作用によって液滴を生じ、分岐型のアクチン繊維の形成を促進する。
(9)ヒトプロテオーム:人間由来のタンパク質群。ゲノムにコードされたタンパク質は大凡2万種存在する。
【論文情報】
掲載誌:Nature Communications
論文タイトル:De novo designed YK peptides forming reversible amyloid for synthetic protein condensates in mammalian cells
著者:T. Miki, M. Hashimoto, H. Takahashi, M. Shimizu, S. Nakayama, T. Furuta and H. Mihara
DOI: 10.1038/s41467-024-52708-5
【研究者プロフィール】
三木 卓幸(ミキ タカユキ) Takayuki MIKI
東京大学 大学院工学系研究科 特任講師
(東京工業大学 生命理工学院 助教(研究当時))
研究分野:ペプチド工学、ケミカルバイオロジー
橋本 匡浩(ハシモト マサヒロ) Masahiro HASHIMOTO
東京工業大学 生命理工学院 大学院生(研究当時)
研究分野:ペプチド工学、ケミカルバイオロジー
三原 久和(ミハラ ヒサカズ) Hisakazu MIHARA
東京工業大学(現 東京科学大学)名誉教授
研究分野:生命科学、ペプチド工学
プレスリリース本文:PDFファイル
Nature Communications:https://www.nature.com/articles/s41467-024-52708-5