 生物環境工学
生物環境工学 木本と草本の個体呼吸と重量のスケーリング式の違いが明らかに
2025-02-28 北海道大学,山形大学,筑波大学,森林総合研究所,北海道教育大学,長崎大学【本件のポイント】 世界各地の草本33種463個体と木本96種1243個体を材料に、芽生えから成熟段階までの個体(地上部と地下部)呼吸(※2)と個...
 生物環境工学
生物環境工学  生物化学工学
生物化学工学 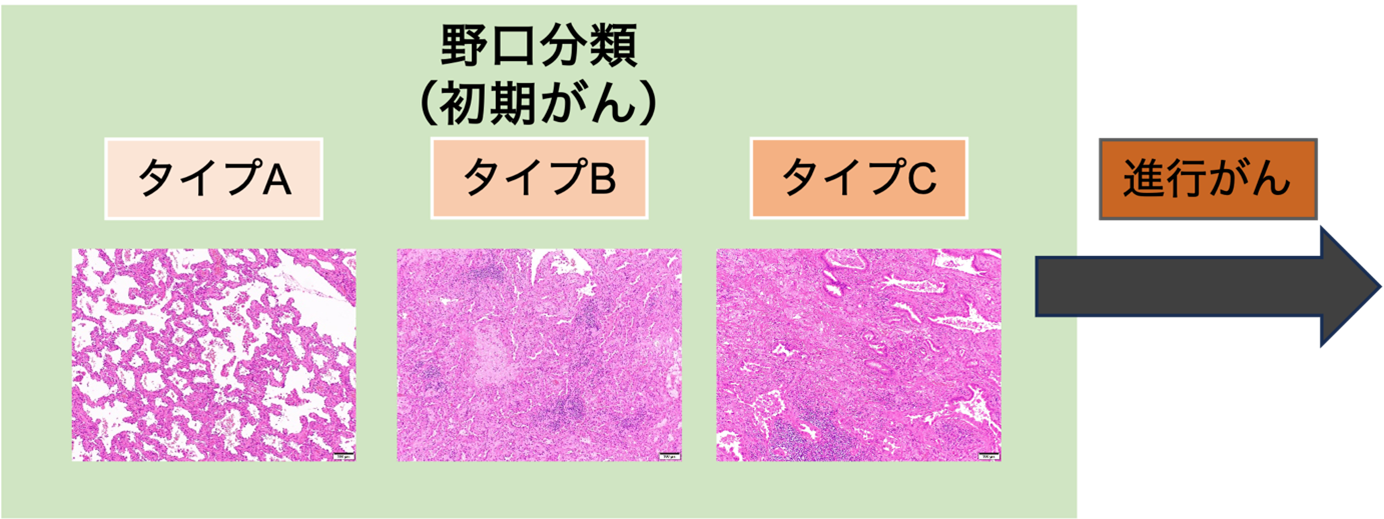 医療・健康
医療・健康 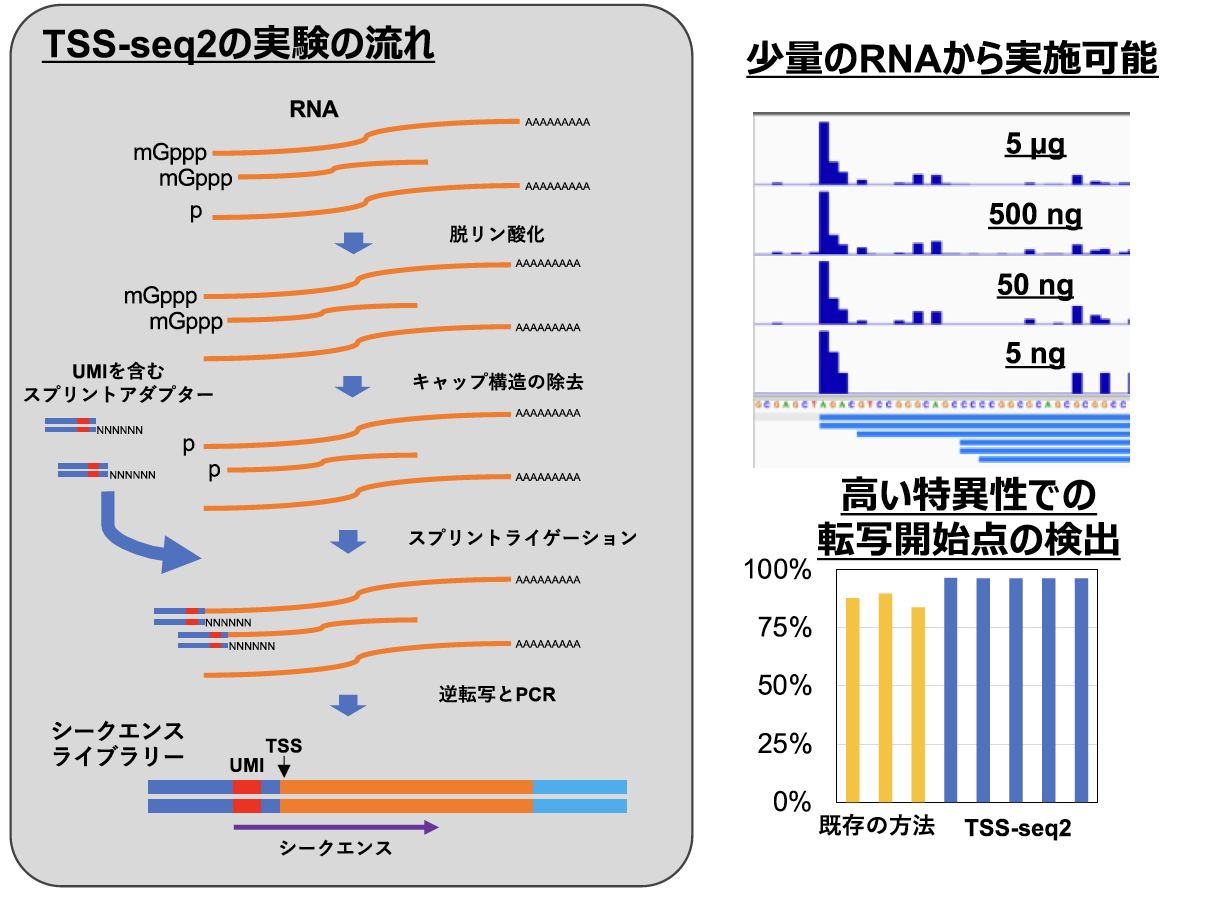 細胞遺伝子工学
細胞遺伝子工学  生物環境工学
生物環境工学 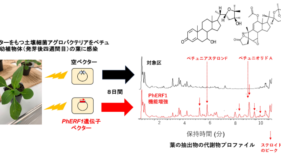 有機化学・薬学
有機化学・薬学 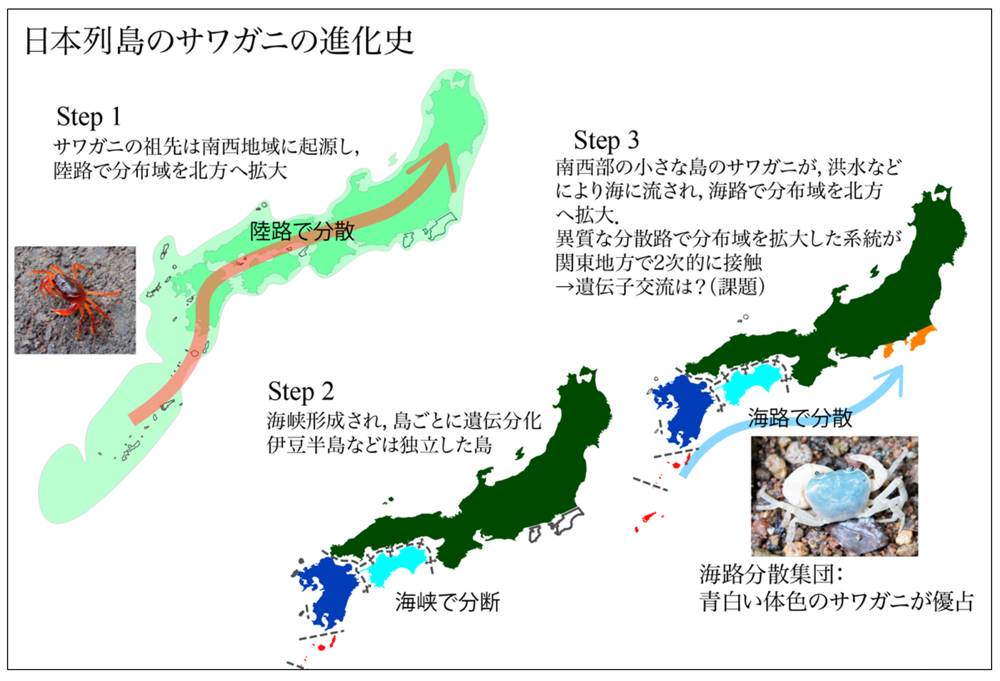 生物化学工学
生物化学工学 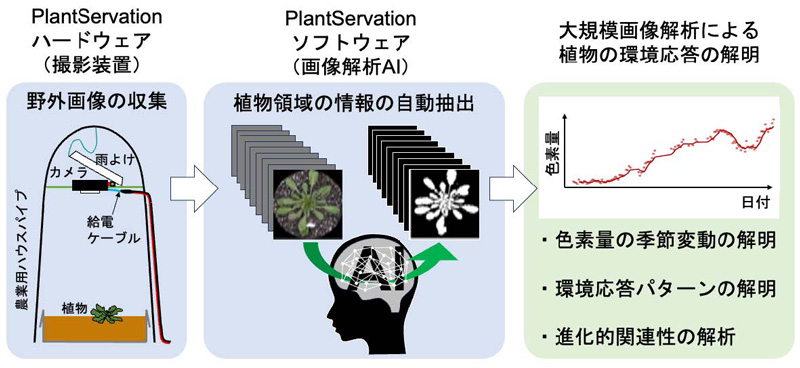 生物環境工学
生物環境工学 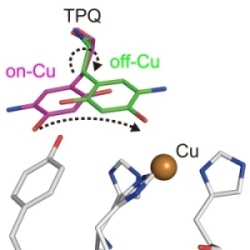 生物化学工学
生物化学工学 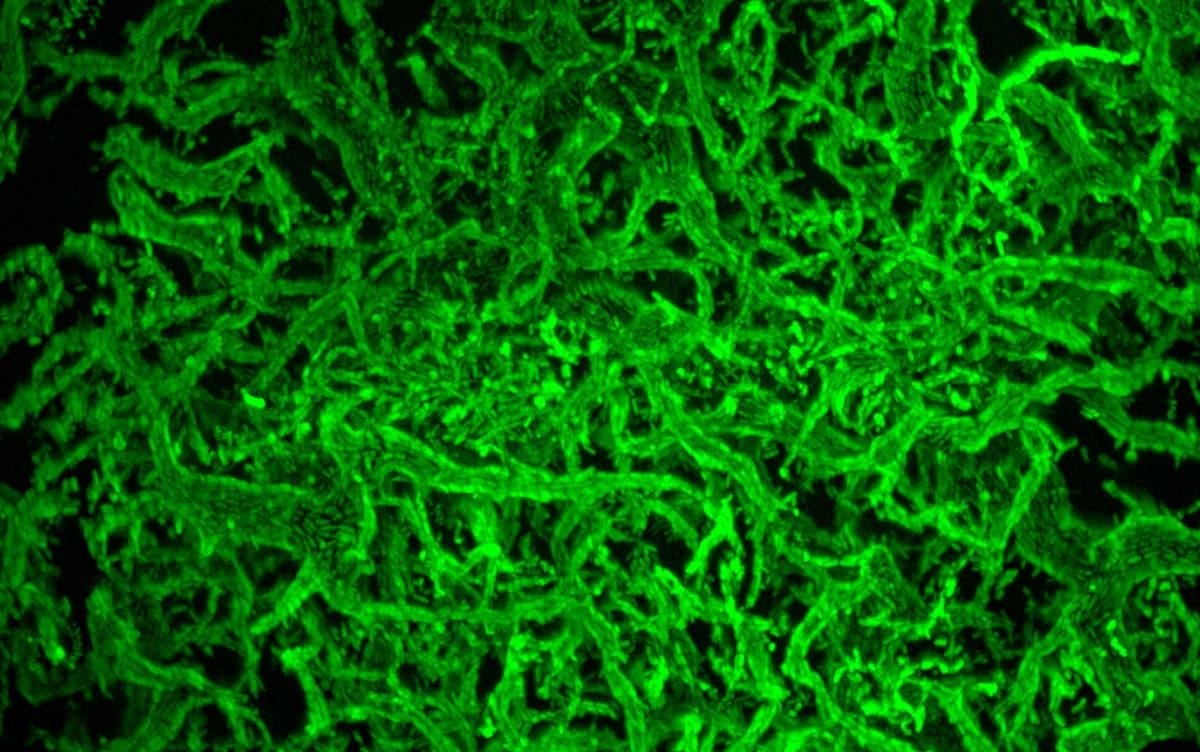 生物工学一般
生物工学一般 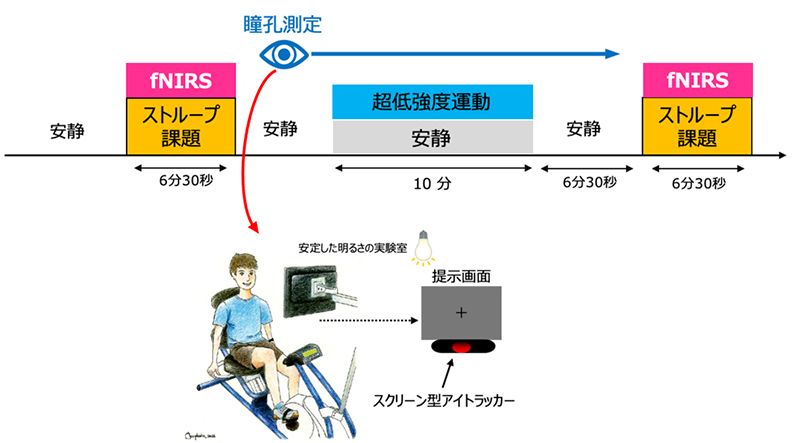 医療・健康
医療・健康 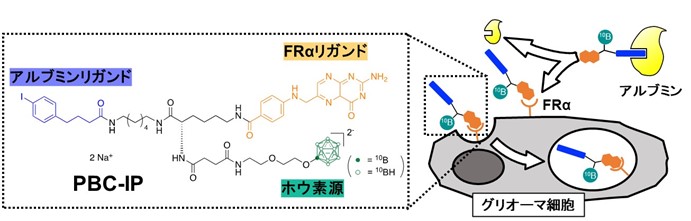 有機化学・薬学
有機化学・薬学