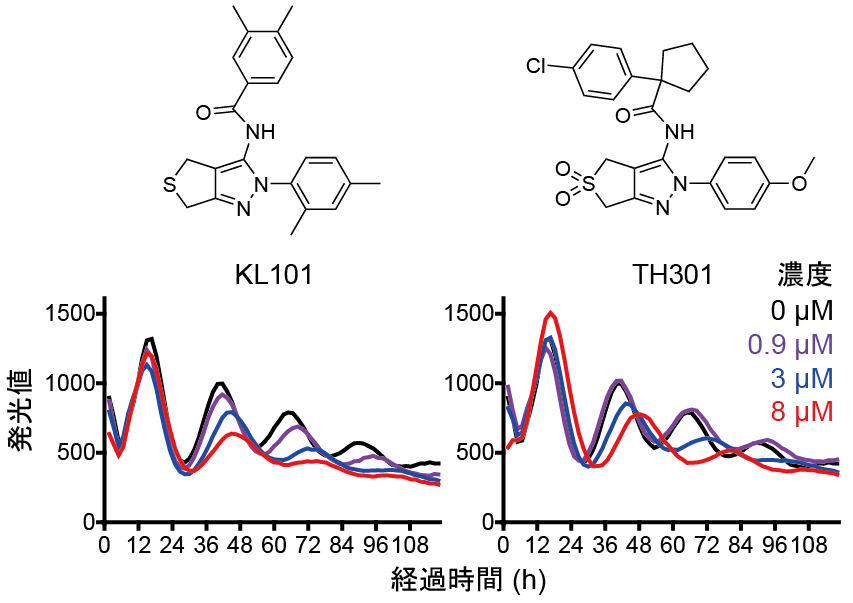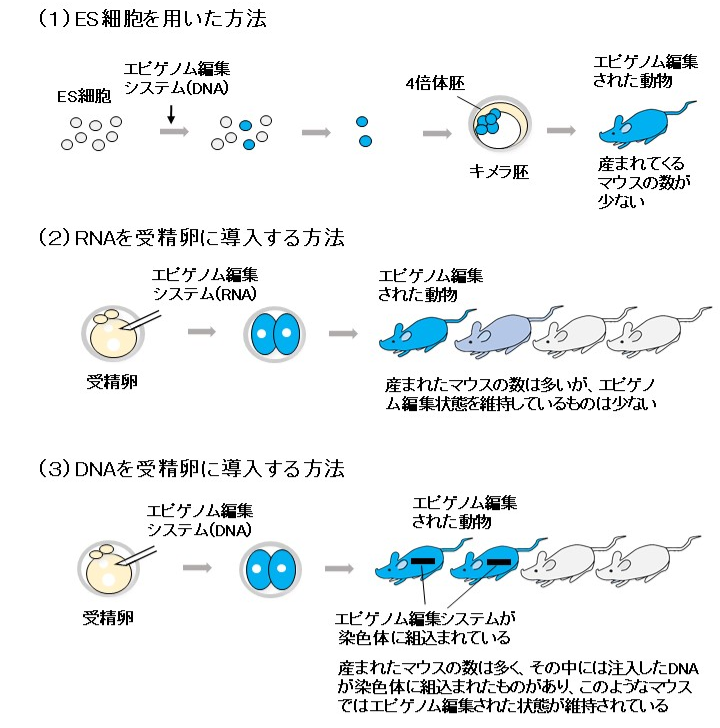2020-03-31 東京大学
インダストリアルデザイナーとして活躍してきた山中先生は、慶應義塾大学にいた2008年に「美しい義足」プロジェクトを開始しました。きっかけは、オスカー・ピストリウス選手の走る姿。パラリンピックでの活躍だけでなくオリンピックへの出場でも知られた、両足が義足の「ブレードランナー」です。
「義足と彼が一体となって疾走するパラリンピック北京大会の動画を見て、目が奪われました。人と人工物のよい関係を追求してきた身には、一つの究極の関係、究極の機能美に思えたんです」
すぐに「義足」「スポーツ」などの語で検索し、ヒットしたのは鉄道弘済会の義肢装具サポートセンターでした。見学に訪れてみて、鉄道業務中に事故に遭った人々の支援に端を発した日本の義足作りの現場には、デザインの概念が未導入であることを実感。スポーツ用義足の第一人者である義肢装具士・臼井二美男さんの真摯な仕事ぶりにも刺激を受け、美しい義足を作る決心をしたのです。
「デザインが必要とされていない世界だったかもしれません。でも、私は過去の制作活動の中で、美しいものを見ると人の反応が変わることを経験していました。企業のデザイナーが手がけにくいものでも大学の研究者なら、という思いもありました」
研究室にチームを立ち上げ、義足ユーザーの生の声を聴く中で出会った陸上選手が、高桑早生さんです。後の有力なパラリンピアンも、当時は幼さの残る高校生。素直に発した「かっこいい義足が欲しい!」という言葉が、多くの難題を抱えるチームを励ましました。
2009年には、陸上競技用下腿義足のコンセプトモデル「ラビット」を展示会で披露。S字の板バネとなめらかな曲面のソケットを持つこの義足は、大反響を呼びました。その後、慶大に進学した高桑選手は山中研究室に加入。義足を用いる選手が隣にいることでプロジェクトが推進されたのは間違いありません。
「あるとき、この義足をつけていると友達が話しかけてくれる、と高桑さんに言われたのがうれしかったですね。たとえば怪我人の痛々しいギプスを見て気軽に話しかけようと思う人は少ないでしょう。でも、デザインはときにその状況を変えることができます」

こちらが「カーボンラビット」(CR1)。「ラビット」の名は、チームの初期メンバーだった学生の命名でした
2013年に東大の生産技術研究所に研究室が移ってから、プロジェクトは新しい次元に入りました。AM(Additive Manufacturing)と呼ばれる技術で美しい義足のマス・カスタマイゼーションを進める。簡単に言えば、3Dプリンターを活用して人それぞれの足に即した義足をたくさん作ろうというアプローチです。
「足の状態や形は千差万別で、義足は義肢装具士が一つ一つ丁寧に調整しないと使えません。それには時間もお金もかかる。長年培われてきた義肢装具士のノウハウを取り入れ、3Dスキャンした足のデータからフィットするソケットを自動作成するCADシステムがあれば、時間とお金を大幅に節約することができます」
チーム山中による入魂のCADシステムは、鉄道弘済会の協力を得て実用テストの段階に入りました。一人一人にフィットする人工物の量産が可能となる日は近づいています。一方、パラ陸上界のエースに成長した高桑選手は、東京大会の出場枠を得る戦いの最中。彼女と一体となって地面を蹴る下腿義足の選択肢には、「ラビット」が進化した「カーボンラビット」も入っています。

「ラビット」の初期モデルとともに走る高桑選手(2010年/鈴木光久氏撮影)