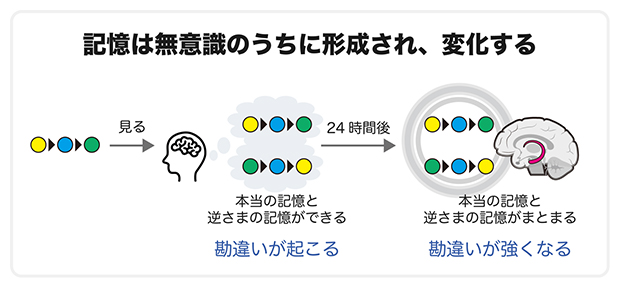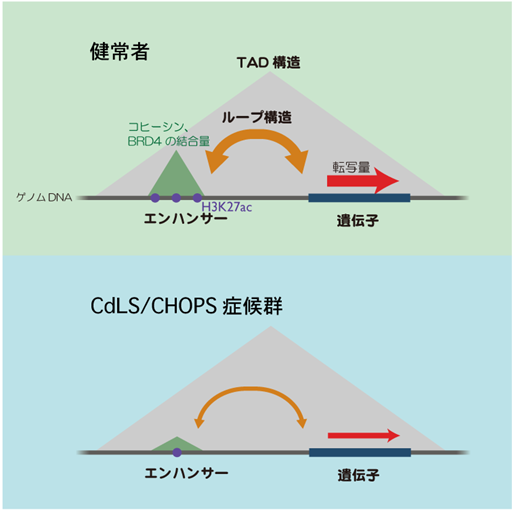2025-02-21 早稲田大学
発表のポイント
- ASDの診断基準の1つである「限定された反復的な行動様式」に相当する「こだわり」や「常同行動」が、日常生活の場面の中に留まらず、動きの予測への選好として視線機能にも反映されることを明らかにしました。
- 図形をなぞる動画を見る際、予測可能な一筆書き動画と、予測不可能ななぞり動画を2つ同時に提示した場合、ASD傾向が高い子どもの方が一筆書き動画を見る割合が、徐々に増える傾向があることを明らかにしました。
- この動画観察は、短時間かつことばを使用せずに適用可能な方法であり、社会的コミュニケーションの困難さがあるとされる児童に対して、より低年齢でのASD傾向の早期発見に寄与することが期待されます。
早稲田大学人間科学学術院の大森 幹真(おおもり みきまさ)准教授は、自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder, ASD)の早期スクリーニングのための行動指標として、予測可能な運動刺激への選好が有用である可能性を発見しました。ASDの診断基準※1には社会性に関する部分とこだわりに関する部分がありますが、こだわりの側面からASDの早期発見を試みる研究はこれまでほとんどありませんでした。そこで本研究ではASD児の社会性の困難さが視線機能に反映するという特徴を活かし、こだわりの特徴も視線機能に反映するかを検討しました。ASDリスク児と非リスク児の両群に、図形をなぞる一筆書き動画およびランダム動画を同時に見ていただき、1つ10秒で約2分間の間に両方を見ていた時間の割合を「好み」(選好:preference)として算出しました。その結果、1つの図形を見る中で、6秒以降の場面ではASDリスク児が一筆書き動画を見る割合が高くなることを発見しました。

図形なぞり動画視聴中の子どもの様子
本研究成果は『Scientific Reports』(論文名:Increased observation of predictable visual stimuli in children with potential autism spectrum disorder)にて、2025年2月7日(金)にオンラインで掲載されました。
(1)これまでの研究で分かっていたこと
ASDの早期発見方法の1つとして、視線機能計測が使用されますが、その中で、ASD児は人のコミュニケーション場面を切り取った「社会的な場面」よりも、人の登場が少ない「非社会的な場面」を長く見ることが明らかになっています。この特徴はASDの診断基準の1つである、「社会的コミュニケーションの障害」を反映していると考えられます。また、非社会的な場面を見る時間が多いASD児は、後にことばの発達の遅れにもつながることが示唆されています※2。
一方で、ヒトとモノを見比べることでASDの特徴を明らかにする研究は多く行われていましたが、ASD児が定型発達児と同程度の時間見るとされているモノ同士での視線機能の特徴はあまり言及されていませんでした。また、もう1つの診断基準であり、後に重篤な問題行動へとつながりやすい「限定された反復的な行動様式」でも、ASD児はモノの反復動作を反映する「繰り返しの動き」の方が「ランダムな動き」よりも長く見ることが明らかになっています。しかし、これまでの研究では「繰り返すことが判明した」後に興味が定着することも示唆しており、いつ、どのような段階で「繰り返す」と予測することができるかは明らかにされていませんでした。そこで、モノ同士を見比べつつ、反復動作につながる動きの予測への興味・関心を視線機能から計測することで、子どもたちの言語能力に依存しない、「グレーゾーン」とされる未診断のASDリスク児の早期発見方法を開発することを着想しました。
(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと
本研究では保護者への質問紙調査から、平均3~4歳のASD傾向があると判定したASDリスク児19名と、傾向なしと判定した非リスク児12名を対象に、2つの動画を同時視聴しているときの視線機能を計測し、それぞれの動画を見た時間の長さから、動画への選好の割合を明らかにすることを目的としました。2つの動画として、各10秒で図形をなぞる際の「一筆書き動画」と「ランダム動画」を複数用意し、合計2分程度視聴してもらいました。視覚的な選好を評価する際に、これまでの研究を参考にして、前半5秒と後半5秒に2分割して分析を行いました。その際、ASDリスク児の方が、後半になるにつれて動きの予測可能な「一筆書き動画」への選好が高くなることを予測しました。その結果、両グループ間で、2つの動画を見ている合計の時間は変わりませんでしたが、ASDリスク児の方が後半5秒間で予測可能な動きを見る割合が非リスク児に比べて高くなることを明らかにしました(図1)。つまり未診断であってもASDリスクのある子どもは、「限定された反復的な行動様式」の特徴を視線機能の面でも反映することが判明しました。さらには、後半5秒間で予測可能な動きを見る割合の高さと、保護者の回答したASD傾向を測定した多くの質問紙項目と正の相関関係にあり、言語発達を評価した多くの質問紙項目とは負の相関関係にあることが判明しました。つまり保護者の困り感などの主観的な印象を、予測可能な動きへの視覚的選好という客観的な方法と関連付けることができる可能性を示しました。さらには、ことばでのやりとりを使用しない非言語的なスクリーニング方法であっても、言語発達の様子も評価できる可能性があることも分かりました。
 図1:予測可能な動きへの視覚的選好を示す画面注視割合と視覚的なヒートマップ
図1:予測可能な動きへの視覚的選好を示す画面注視割合と視覚的なヒートマップ
(3)研究の波及効果や社会的影響
本研究の成果は次の3点において波及効果や社会的影響につながると考えます。
① 研究面として国内外に対して動きの予測性への視覚的選好がASDの診断基準の1つである「限定された反復的な行動様式」を反映している可能性を示したことで、これにより一層多角的なASDの理解や病態の解明にも寄与できる。
② 臨床的意義として2分程度の動画視聴による視覚的選好の非言語的評価がASDリスク児の早期発見指標として活用できる可能性を示したことにより、質問紙による過剰な主観的評価の排除や、言語発達が未熟なより低年齢の子どもたちに適用可能になると考えられる。
③ 社会的意義として、ASDの早期発見に寄与すること期待できる。
現在でも我が国のASD診断のボリュームゾーンは3歳前後ですが、未診断や経過観察の選択等もあり、平均的な診断時期は6~7歳とされています※3。そのため、本研究の成果が医師の診断を補助することにつながり、より早期の段階で適切な支援を提供することにつながって欲しいと思います。
(4)今後の課題
今回の対象児は未診断でASDリスクが高い子どもを対象にしていたため、今後の研究では実際にASD診断がされている子どもたちで同様の結果が見られるかを検証する必要があります。また、本研究では3歳前後の子どもを対象にしていましたが、参加者の年齢層が1歳から5歳と幅広く、年齢ごとの変化を見ることが難しかったため、今後の研究ではより年齢層の厳密性が必要と考え、乳幼児健診での法定健診の対象年齢となる1.6歳児や3歳児を中心に参加を募集し、予測可能な動きへ視覚的選好の発達的な変化を明らかにしたいと思います。
(5)研究者のコメント
私は発達臨床心理学・応用行動分析学を基盤にした発達障害児への支援が専門であり、早期支援の方法論は業界の中で蓄積されています。今回のように早期発見の方法が増えることで、経過観察を選択せずに、より円滑に早期支援へとつなげるための選択肢を提供できたと考えています。予測可能な動きへの選好や注目は、日常・保育・教育場面でも比較的観察がしやすい特徴であると考えますので、本研究の成果がお子さんや保護者の行動変容のきっかけになることを願い、これからも研究を進めていきます。
(6)用語解説
※1 自閉スペクトラム症の診断基準(DSM-5-TRより)
基準A:持続する相互的な社会的コミュニケーションや対人的相互反応の障害
基準B:限定された反復的な行動、興味、または活動の様式
基準CとD:これらの症状は幼児期早期から認められ、日々の活動を制限するか障害する
※2 自閉スペクトラム症児における視線機能の生態学的指標としての評価
出典:Wen, T. H., Cheng, A., Andreason, C., Zahiri, J., Xiao, Y., Xu, R., … & Pierce, K. (2022). Large scale validation of an early-age eye-tracking biomarker of an autism spectrum disorder subtype. Scientific Reports, 12, 4253. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-022-08102-6
※3 日本における自閉スペクトラム症の診断年齢について
出典:Kurasawa, S., Tateyama, K., Iwanaga, R., Ohtoshi, T., Nakatani, K., & Yokoi, K. (2018). The age at diagnosis of autism spectrum disorder in children in Japan. International Journal of Pediatrics, 2018, 5374725. doi: https://doi.org/10.1155/2018/5374725
(7)論文情報
雑誌名:Scientific Reports
論文名:Increased observation of predictable visual stimuli in children with potential autism spectrum disorder
執筆者名(所属機関名):大森幹真(早稲田大学)
掲載日時:2025年2月7日(金)
掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41598-025-89171-1
DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-89171-1