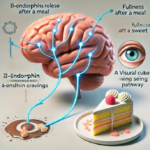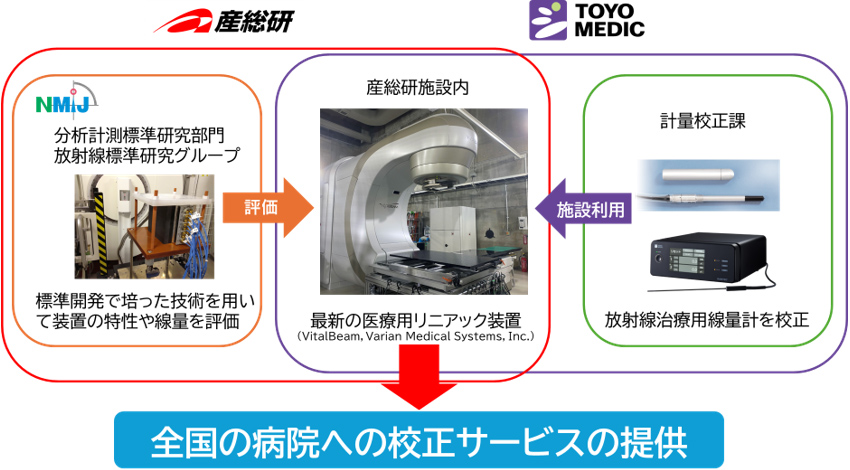2025-02-04 国立遺伝学研究所
外来種の分布域の拡大は、人為的な導入とそれに続く分散の繰り返しによって生じます。分散は人為的な介入がなくても生じ、そのパターンは種によって異なります。そのため、外来種のさらなる分散の防止や効率的な管理のためには、個々の種について、分散の様式に関する知見を蓄積していくことが重要です。
この度、国立遺伝学研究所の福家悠介(日本学術振興会特別研究員PD)と香川大学大学院農学研究科の石井良典氏(修士課程学生)は、世界的に問題となっている淡水性甲殻類の侵略的外来種シナヌマエビ(以下、外来エビ)について、水系内における分布拡大に関する知見を遺伝解析と形態解析に基づいて報告しました。調査地とした兵庫県夢前川水系では、約30年前にも十脚甲殻類の分布調査が行われており、当時は外来エビと同属の在来種ミナミヌマエビ(以下、在来エビ)が水系全域に生息していたことが分かっています。しかしながら、今回の調査では、在来エビは主にダムの上流側の地点でのみ出現し、ダムより下流のほとんどすべての地点は外来エビに置換されていることが示唆されました。外来エビはダムの下流側に導入されたことが過去に報告されています。本研究は外来エビの強い侵略性とそのパターンの一端を浮き彫りにすることができました。すなわち、外来エビが一度導入されると在来エビと完全に置き換わってしまうこと、そして、本水系では、一般的に生息地の分断などによって生態系に負の影響を与えるダムが上流側に残る在来エビの生息地への外来種の分布拡大を防いでいることを明らかにしました。
 図:在来種ミナミヌマエビNeocaridina denticulata。本研究で調査した水系では、近縁の外来種に追いやられ、ダムの上流側のみで確認された。
図:在来種ミナミヌマエビNeocaridina denticulata。本研究で調査した水系では、近縁の外来種に追いやられ、ダムの上流側のみで確認された。
River dam prevents the invasion of non-native species of Neocaridina Kubo, 1938 (Decapoda: Caridea: Atyidae) into native habitats: A case study in the Yumesaki River system, Japan
Ryosuke Ishii and Yusuke Fuke *
* Corresponding author
Journal of Crustacean Biology (2025) 45, ruaf009
DOI:10.1093/jcbiol/ruaf009