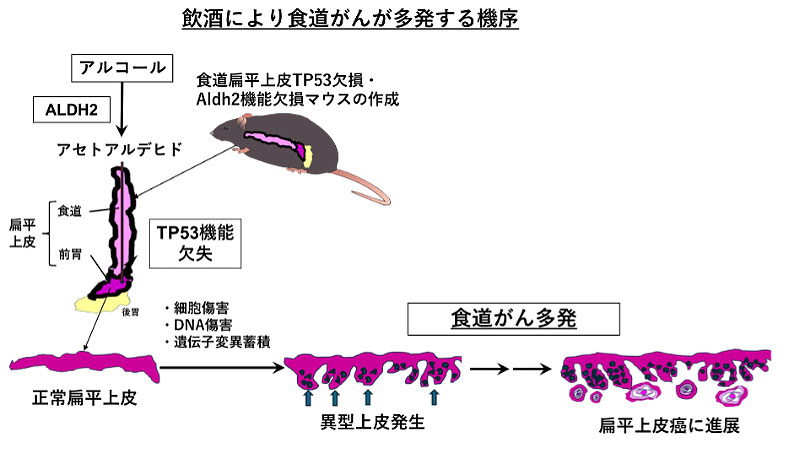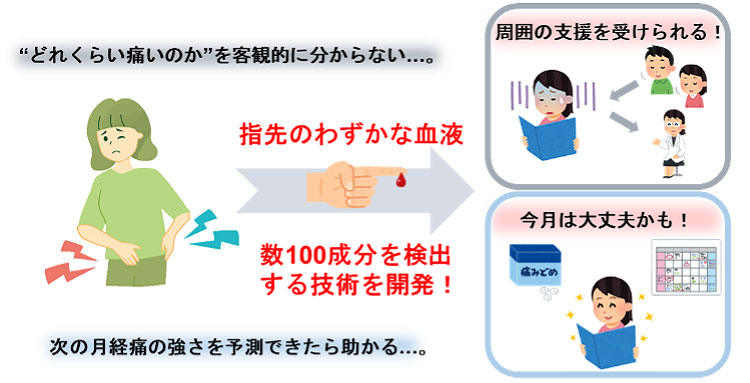2025-02-14 京都大学
近年、死後脳研究は神経疾患や精神疾患の解明に重要な役割を果たしています。こうした研究活動には、研究参加に協力する人の存在が欠かせません。一方、日本では、解剖写真のSNS投稿が大きな話題になったように、身体の取り扱いや流通のあり方について、多くの人々が関心を持っています。
井上悠輔 医学研究科教授らは、研究に参加する意思を表明した市民・患者の視点に寄り添い、その背景や関心をより深く知る作業が研究側にも求められると考え、東京都健康長寿医療センターのブレインバンク(死後脳のバンク)への提供意思を登録した88名を対象に郵送調査を実施し、52名から回答を得ました(回答率59.1%)。
本研究は死後の身体提供の意向を表明した個人の想い・懸念に迫ったアプローチ自体が極めて貴重なものであり、ご本人の関心や懸念に応じたコミュニケーションの重要性、家族向けガイダンスの充実や、研究成果の定期的な発信の重要性が明確になりました。今回はヒアリングの一報であり、今後もインタビュー調査などを通じてより検討を深める取り組みを続ける予定です。
本研究成果は、2025年2月7日に、国際学術誌「Neuropathology」にオンライン掲載されました。
研究者のコメント
「本研究の発表にあたり、遺体研究やブレインバンクは、医療・研究と社会との間にあり、一つ一つの出会いを大事にして積み上げられてきたものであることを改めて実感しております。
解剖や死後の研究参加の話は、年末の報道では大きな話題になりましたが、従来、社会的に注目を集めることは多くありません。世代をまたいで、患者・家族と医療者・研究者との共同作業で活動が積み重ねられていることや、今後も続けていくためにどのような取り組みが必要かを、引き続き考えていきます。
これまで、研究倫理の文脈でも、『遺体』や『死後』の話はほとんど議論されてきませんでした。その人が生きていることを前提とした配慮・保護の議論の延長のみで、医学研究をカバーし切れるのか、わたしは問題意識を持ってきました。死後の研究参加は人や他者を信頼し、そこに託す視点が強くなります。この視点は、ブレインバンクに限らず、現在・将来の研究活動にとって大きな広がりがある概念だと考えています。」(井上悠輔)
詳しい研究内容について
ご遺体に学ぶ医療・医学研究を⽀えるもの―解剖・死後の⾝体提供を表明した⼈々52名の証⾔の検討―
研究者情報
研究者名:井上 悠輔
書誌情報
【DOI】https://doi.org/10.1111/neup.13030
【書誌情報】Yusuke Inoue, Maki Obata, Maho Morishima, Shigeo Murayama, Yuko Saito (2025). Bridging minds: Participant perspectives on postmortem brain research and engagement. Neuropathology.