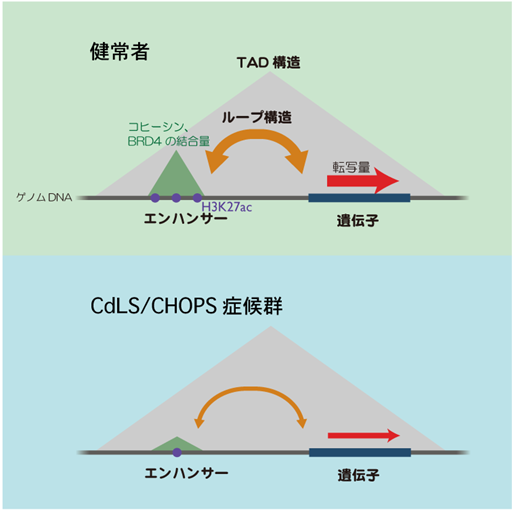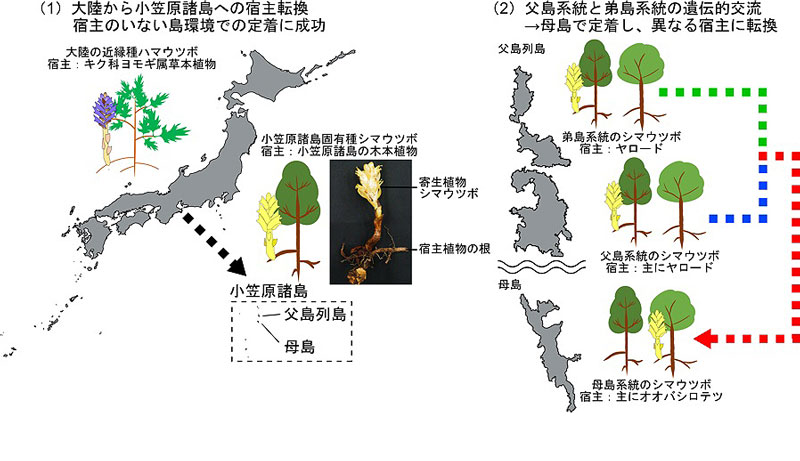2025-02-20(2025-03-05更新) 国立がん研究センター
発表のポイント
- 国立がん研究センター中央病院では、希少がんの産学共同プロジェクトのMASTER KEYプロジェクトの枠組みで、AYA世代での発症が多い超希少な胞巣状軟部肉腫に対する第II相医師主導治験を国内4施設で実施しました。
- 本医師主導治験の成績などが審査され、胞巣状軟部肉腫では国内初となる免疫チェックポイント阻害薬アテゾリズマブが成人及び2歳以上の小児で薬事承認されました。
- 国立がん研究センター中央病院はMASTERKEYプロジェクトの取り組みを通し、希少がんの患者さんにより早くより多くの新薬を届け、日本の医薬品を取り巻くドラッグラグ問題の解決に向けて引き続き取り組んでまいります。
概要
国立研究開発法人国立がん研究センター(理事長:中釜 斉、東京都中央区)中央病院(病院長:瀬戸 泰之)は、希少がん注1の産学共同プロジェクトMASTER KEYプロジェクトの枠組みで、胞巣状軟部肉腫に対する免疫チェックポイント阻害薬アテゾリズマブの有効性と安全性を検討する第II相医師主導治験(試験略称:ALBERT;以下ALBERT試験、試験番号:NCCH1907)を当院含む国内4施設で実施しました。
この度、ALBERT試験の成績およびアメリカの国立がん研究所主導の第II相臨床試験の成績をもとに、胞巣状軟部肉腫では国内初となる免疫チェックポイント阻害薬アテゾリズマブが成人および2歳以上の小児の切除不能な胞巣状軟部肉腫に対して2025年2月20日に薬事承認されました。この承認申請には国立がん研究センター中央病院などで実施する、「小児・AYAがんに対する遺伝子パネル検査結果等に基づく複数の分子標的治療に関する患者申出療養」(以下、PARTNER試験)の情報も提出されました。
胞巣状軟部肉腫は思春期および若年成人(AYA世代注2)に発症が多く、治療法は手術による完全切除が基本です。手術の適応にならない胞巣状軟部肉腫に対しては、アメリカでは2022年12月に免疫チェックポイント阻害薬のアテゾリズマブが薬事承認されましたが、日本ではドラッグラグの状況が続いていました。
今回の薬事承認によりアメリカに続き日本でも、成人及び2歳以上の小児の切除不能な胞巣状軟部肉腫の患者さんに対して免疫チェックポイント阻害薬アテゾリズマブが使用できるようになり、患者さんの治療選択肢が増えました。
胞巣状軟部肉腫(ほうそうじょうなんぶにくしゅ)
胞巣状軟部肉腫は、全国骨・軟部腫瘍登録一覧表(2022年)によると、2006~2022年の17年間に登録された症例は263例と非常に稀ながんでAYA世代での発症が多くみられます。主に、四肢、大腿前面や臀部などの深部軟部組織に多く発生し、特に太ももが好発部位とされています。
胞巣状軟部肉腫に対する治療法は、手術による完全切除が基本ですが、切除不能の場合は有効な薬物療法はなく、基本的には緩和治療のみが実施されていました。
ALBERT試験
ALBERT試験は、2020年から国立がん研究センター中央病院が主導で行った国内4施設による切除不能胞巣状軟部肉腫に対するアテゾリズマブ療法の多施設共同第II 相医師主導治験です。2019年にアメリカ国立がん研究所からの、切除不能胞巣状軟部肉腫に対するアテゾリズマブの有効性の示唆に関する報告をもとに試験が組み立てられ、好発年齢である16歳以上の切除不能な胞巣状軟部肉腫の患者さんを対象に実施しました。20名の患者さんのうち2名に完全奏効が認められ、主な副作用は発熱やリンパ球減少で、いずれもコントロール可能な事象でした(参考:CTOS 2023. Abstract #1571824)。
ALBERT試験はMASTER KEY プロジェクトの枠組みを用い、中外製薬株式会社から資金および薬剤の提供を受けて実施しました。
MASTER KEYプロジェクト

希少がんは、一つ一つのがんの患者数が少なく臨床試験もあまり行われてこなかったため、標準治療が十分に確立されておらず、患者さんにとっては新しい薬を受けられる機会が限られていることが問題となってきました。2017年から開始したMASTER KEYプロジェクトは、この世界共通の課題に国立がん研究センターと製薬企業が共同で取り組み、希少がんの患者さんに、より早く、より多くの新薬を届けることを目指しています。
MASTER KEYプロジェクトでは、2025年1月31日時点で、固形がん4,096例、血液がん494例の遺伝子情報や診療情報、予後データなどを網羅的に収集し、希少がんにおける日本最大のデータベースを構築しています。このデータベースは治療開発の参考資料とされ、将来の患者さんのための重要な情報となっています。またデータベースを活用し33件(うち実施中6件)の医師主導治験・企業治験を実施しています。解析終了した臨床試験から、希少な遺伝子変異に対するがん種横断的治療薬が日本で薬事承認され、希少がんの治療開発を加速させる基盤となっています。
MASTER KEYプロジェクトの詳細はこちらをご覧ください。https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/masterkeyproject/index.html
PARTNER試験
PARTNER試験は、2024年1月に開始された難治性小児・AYA 世代がん患者さんを対象とした適応外薬あるいは未承認薬を投与する臨床研究で、患者申出療養制度下で実施しています。使用する医薬品は、すでに国内または海外で小児を対象とした臨床試験が行われており、小児における一定の安全性情報がある医薬品を対象としています。国内で小児に対する用法・用量等が定められていない医薬品については、海外で承認されている小児に対する用法・用量等や小児に対する国内や海外の治験等をもとに用法・用量を決めています。
現在、国立がん研究センター中央病院含む4施設で実施され、対象医薬品は、5社から8医薬品を無償提供いただき実施しています。アテゾリズマブもPARTNER試験の対象医薬品の一つであり、今回の薬事承認では、PARTNER試験でのアテゾリズマブの投与経験データも提出されました。
PARTNER試験の最新の情報はプレスリリースをご覧ください。
2024年12月26日:小児・AYA 世代を対象とする患者申出療養「PARTNER 試験」が岡山大学病院でも開始-小児・AYA 世代がん患者のドラッグアクセスの改善を目指す‐ https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2024/1226/index.html
用語解説
注1 希少がん
一般に人口 10 万人当たり6例未満で、数が少ないため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きい疾患を指します。希少がん全体では全がん患者推定罹患率の9~22%を占めますが、それぞれの希少がん疾患は、非希少がんの8~10分の1の推定罹患率であり、研究・薬剤開発がなかなか進まない状況にあります。本試験の対象疾患である胞巣状軟部肉腫のように、1年間に発症する患者が100万人あたり数名程度のがんは、希少がんの中でも発症患者数がより少ない「超希少がん」と言われることがあります。
注2 AYA世代
AYA(アヤ)世代とは、Adolescent & Young Adult(思春期・若年成人)のことをいい、概ね15歳から39歳の患者さんに当たります。小児に好発するがんと成人に好発するがんがともに発症する可能性がある年代であり、肉腫など、AYA世代に多い特徴的ながんも存在します。従って、この年代のがんの診療には、小児および成人専門の医師、看護師をはじめ、多職種が連携して診療を行うことがとても重要です。また患者さんも中学生から社会人、子育て世代とライフステージが大きく変化する年代であり、患者さん一人ひとりのニーズに合わせた支援が必要となってきます。
参考情報
中外製薬株式会社 プレスリリース
テセントリク、超希少な疾患である胞巣状軟部肉腫への適応拡大が承認(2025年2月20日)(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ先
研究に関する問い合わせ
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
臨床研究支援部門 研究企画推進部 臨床研究支援室
ALBERT試験調整事務局
広報窓口
国立研究開発法人国立がん研究センター 企画戦略局 広報企画室